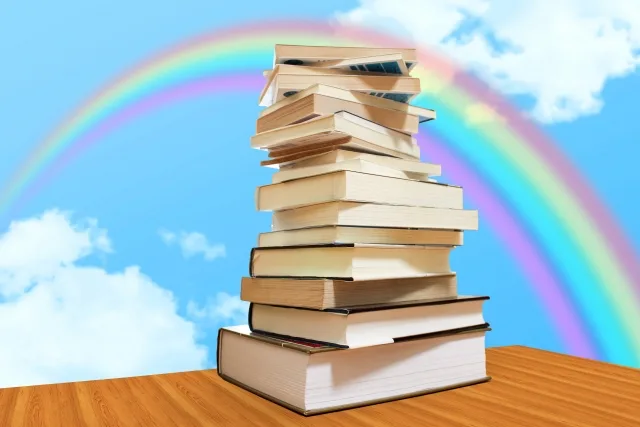
夏休みの宿題で、時間がかかる大物の代表といえば‥読書感想文ですよね。
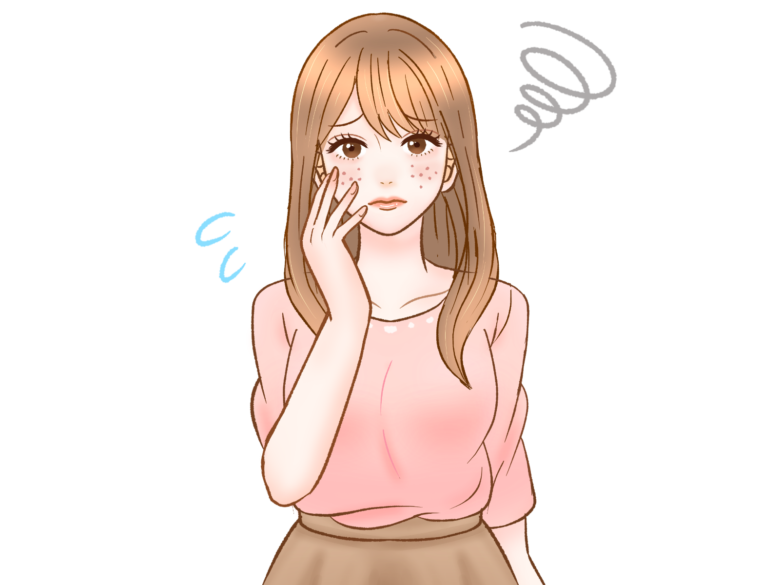
わが家でも毎年取り組みますが、書き上げるまで結構大変です。
本を選び・・本を読み・・内容を自分の中でまとめ・・感想をまとめる。
これを子どもが全て自分の力でやるのは難しいですよね。
わが家では、子どもがやる気になるような声掛けと、構成の考え方や子どもの感想を引き出すことなどをサポートしています。
小学校6年間、2人の子ども達は作文で様々な賞に入賞することができました。
わが家で実践しているやり方をまとめました。
*このやり方で書いても必ず入賞できるものではありませんので、参考にしていただき素敵な読書感想文を仕上げていただければ幸いです。
読書感想文の書き方の3つのポイント

冒頭は「セリフ」がおすすめ

書き出しのインパクトはとても大切です。
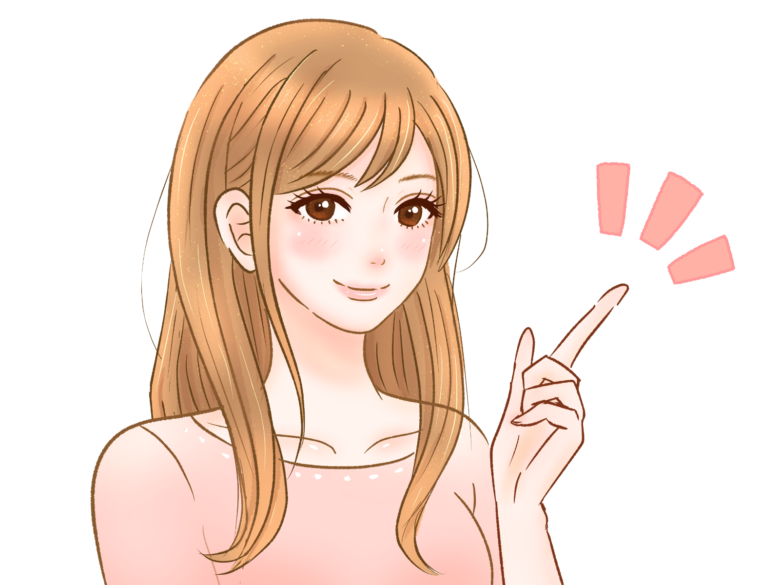
わが家の子たちは、このテクニックを覚え実践しています。
例えば、「にゃーご」という宮西達也先生の絵本を題材にした時
「にゃーご」
と大きな声が聞こえた場面で、ぼくはとてもびっくりしました。
冒頭はこのように書き出しました。
「にゃーご」とは文中に出てくるセリフです。
この部分を読むと、作文を読んでいる方はなんでびっくりしたのかな?
「にゃーご」ってなに?などと続きが読みたくなります。
本文の中のセリフをそのまま引用してもいいですし、自分のセリフを書いてもどちらでも有効的です。
セリフ以外にも擬音語や効果音などを冒頭に入れ、読んでいる人の興味を引き出すことがポイントです。
あらすじをダラダラと書かない

よくやってしまいがちですが、感想文なので本の内容を長々と説明するのはNGです。
読んでいる人に内容が分からないと感想も伝わらない部分もあるので、ザックリとした内容を書くのはOKです。
しかし、冒頭からのあらすじの説明はあまりお薦めしません。
あらすじや本の内容を書く場合は、冒頭ではなく途中で感想と絡めて書くのがよいです。
評価する方にもよりますが、あらすじが長く書いてあるだけで「感想文ではない」と判断されてしまう場合もあります。
その本を読んで自分が変わった点を書く

後半部分には、その本にどういう影響を受けたのかを書きます。
例えば、
「こんなことがあったら、私だったら○○はできないと思います。でも、主人公の□□は○○していてすごいと思いました。私も、□□のように勇気を出してやってみようと思います。」
このような感じで、主人公の行動に影響を受けて、自分がどのように変わったのかを書きます。
上記の例えは短いですが、実際はもっと詳しく長めに書くと良いと思います。
これからの前向きな目標なども書けるとさらにいいでしょう。
子どもをやる気にさせるポイント

本を選ぶポイント
なるべく本の文字が多くなく難しくない本を選びます。
わが家の上の子は本をあまり読まなかったので、分厚い本や文字が細かい本は、読み終えること自体がハードルが高かったです(笑)。

小学校1年生の時は絵本で書きました。
絵本は、読み取る内容が多いのに、とてもまとめやすいので低学年のお子さんにはおススメです。
もちろん、普段から本をよく読み、文字数が多くても負担にならない子であればどんな本でも良いと思います。
分厚い本の場合は全てをまとめようとするとハードルが上がりますので、自分の印象に残った章に焦点をあてて書くことがオススメです。
あとは、図書館や本屋さんなどで子どもと一緒にじっくり選ぶことです。
親が読んでほしい本があっても、子どもが読みたい気持ちがなければ感想文も進みが悪いです。
子どものやる気が出るように、子どもが自分で本を選ぶことが大切です。
感想文が分からない子への声掛け
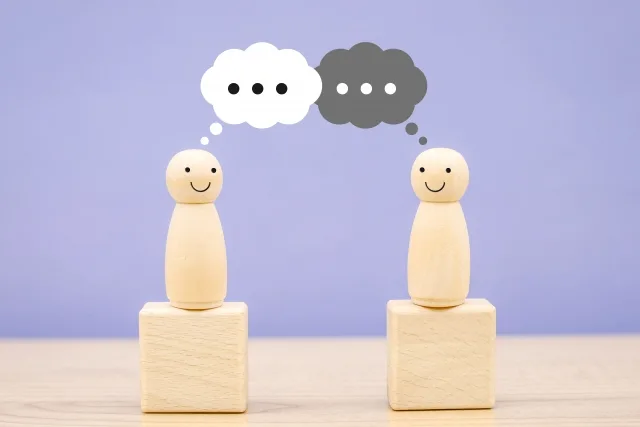
急に「なんでもいいから感想書いてごらん」と言われても、ほとんどの子は書けません。
まずは、親の声掛けで何が感想なのかを理解できるように質問します。
質問を色々広げていきながら、子どもがどこに一番感銘を受けたかを探ります。
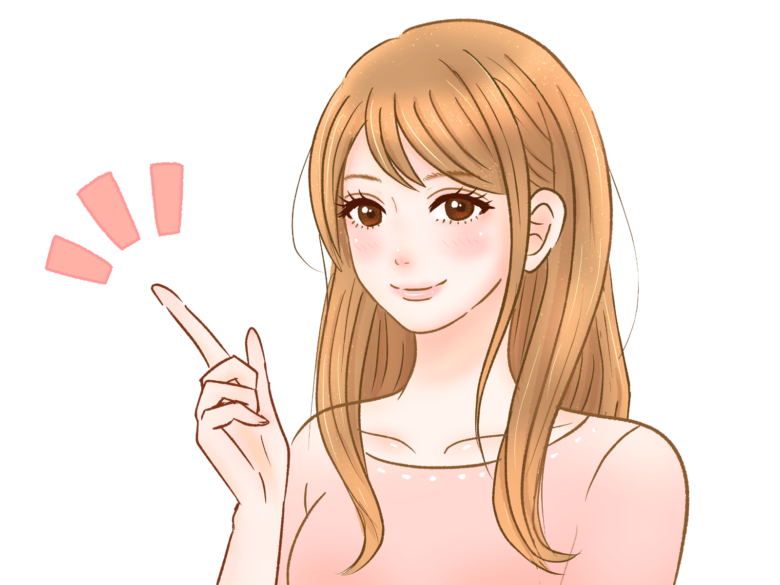
聞き出したことをメモ書きしておくと後で整理しやすいです。
質問に答えることで子どもの頭が整理され、自分の感想を自分で理解することができます。
高学年であれば、親も一度本を読んで一緒に本の感想を話すだけでも、子どもの感想や意見はどんどん溢れてくると思います。
構成を一緒に考える

子どもが一番感銘を受けたところから、全体的な方向性が決まると思います。
感想文の全体を3~4ブロックに分けて考えます。
- 一番大きな感銘を受けたところの感想(書き出しはインパクト重視)
- 簡潔にまとめた本の内容や、その他の感じたことなど
- 似たような自分の体験などがあれば書く
- 自分がどのように変わったのか、どうなりたいかなど
上記は一例で、子どもとの質問タイムで書き出したいことが見つかれば、3~4個に分けて構成を考えてみてください。
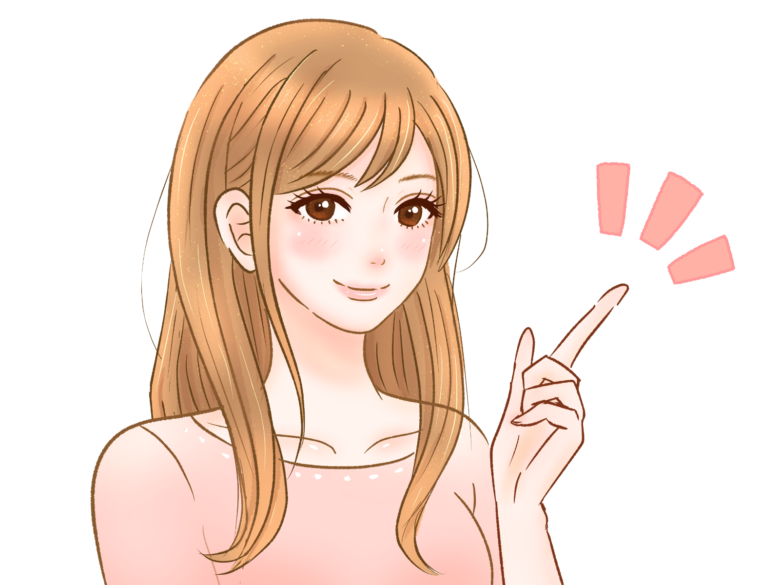
本をみながら、気になったところには付箋を貼っておくとスムーズです。
感想文の注意点
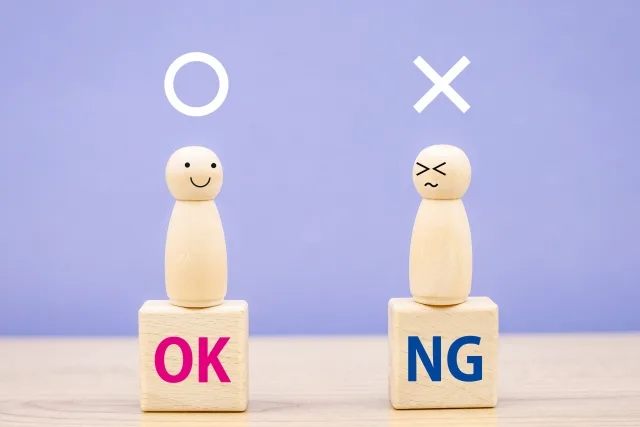
読書感想文を子どもと一緒に取り組んでいると、「もっとこう書いてほしい」「ここはこういう気持ちを書けばいいのに」などと出てくると思います。
しかし、親の感想文ではなく子どもの感想文です。
そして、あまり口出しをすると子どもは「自分で考えた文はダメなんだ」と感じてしまいます。
あくまで、「子どもが分からないことをサポートする」ということを忘れないでください。
「こういう風に思うんだけど、どんな風に書けばいい?」
「こういう気持ちって、何かいい言葉ある?」などと表現方法などを聞かれた時は教えてあげてください。
親がみてあげることが難しい場合は「ブンブンどりむ」を活用するのもオススメです。
第71回青少年読書感想文全国コンクール【課題図書】を紹介

1・2年生【小学校低学年の部】
ライオンのくにのネズミ
ライオンの学校に転校してきたネズミのぼく。体の大きさも、言葉も違うライオンと仲良くなんてできっこない!そう思っていたけど…
ぼくのねこ ポー
道でひろったねこを、僕の家で飼うことにした。だけど、転校生の森くんが、飼っていたねこがいなくなったと話していて…
ともだち
ぼくはエトは大の仲良し!どんな日も「ふたりいっしょ」
ある日、一人の男の子が「仲間に入れてくれる?」とやってきて…
ワレワレはアマガエル
おどろきの生態や体のとくちょうを、アマガエル自身が愛嬌たっぷりに紹介。オタマジャクシからカエルへの返信も、大迫力!
3・4年生【小学校中学年の部】
ふみきりペンギン
ペンギンの声を聞く子。うわさ話を確かめたい子。鏡でライオンに会う子。変わったフクロウを見る子。自分らしさってなんだろう?
バラクラバ・ボーイ
バラクラバ帽をかぶった転入生のトミーがやってきた。なぜトミーは帽子をかぶってるの?あの帽子の下には何がかくされている?
たった2℃で…地球の気温上昇がもたらす環境災害
気温が2℃上がると、地球でくらす生き物みんなの命があぶない!植物も動物も、あなたも、わたしも。一緒に考えよう!
ねえねえ、なに見てる?
同じ場にいても、見ているもの、その見え方は全く違う。食卓を囲む家族の異なる世界を描く、多様性と共感について知る絵本。
5・6年生【小学校高学年の部】
ぼくの色、見つけた!
ぼくは生まれつき、みんなと同じようには色が見えていないらしい。悩みを持つ全ての子に読んでほしい、心が軽くなる物語。
森に帰らなかったカラス
少年ミックが手当てをしたカラスのヒナは、ケガが治ったあとも家に戻ってくるように…。少年とカラスのふれあいの物語。
マナティーがいた夏
11歳の夏休み、ピーターはすべてうまくやれるはずだった。けがをしたマナティーも救えるはず。変化に向き合う勇気をくれる、成長物語。
とびたて!みんなのドラゴン難病ALSの先生と日明小合唱部の冒険
難病ALSと闘う先生と小学生たちが合唱全国大会を目指す!人前で話せない内気なマナミや仲間たちの冒険と成長を描く感動実話。
【中学校の部】
わたしは食べるのが下手
会食恐怖症と摂食障害。ふたりの少女がたどり着いた正しい”食”との向き合い方とは。わたしたしが望む給食って、どんなだろう?
スラムに水は流れない
インドのスラムは水の供給が極端に悪かった。少女ミンニは水関連の事件や母が倒れるなど試練の中、健気な生きぬいていく。
鳥居きみ子家族とフィールドワークを進めた人類学者
「知の巨人」ともいわれた夫の鳥居龍蔵や家族とともに、人類学の研究に取り組み、調査を進めた鳥居きみ子の生きざまを描きます。
【高等学校の部】
銀河の図書室
宮沢賢治の言葉を残して、突然学校から消えてしまった先輩。その謎を追う高校生たちの今を瑞々しく描く、傑作青春小説。
金原瑞人選モダン・クラシックYA夜の日記
成績に一喜一憂する日々には、はじめてのホントの恋!ハードな高校生活を生き抜くために、「優等生」のジュノが見つけた法則とは?
「コーダ」のぼくが見る世界聴こえない親のもとに生まれて
もし、親の耳が聴こえなかったら。なんて想像もつかなかった。言葉やコミュニケーションの本質、「善意による差別」ってなんだろう?
2025年「夏休みすいせん図書」はこちらで紹介しています。
まとめ

夏休みの大きな課題である読書感想文。
作文が得意な子はスラスラと書けると思いますが、多くの子は苦手だと思います。
しかし、いくつかのポイントを抑えると、審査員の目にとまる作品ができると思います。
・冒頭は「セリフ」がオススメ
・あらすじをダラダラと書かない
・その本を読んで自分が変わった点を書く
・難しすぎない本を選ぶ
・質問をして子どもの気持ちを引き出す
・構成は一緒に考える
子どもに宿題をやる気にさせること、やる気を継続させることは親にとっても大変なことですよね。
親がみてあげることが難しい場合は「ブンブンどりむ」を活用する手もあります。
子どものやる気を引き出すコーチングスキル↓も参考にしてみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。

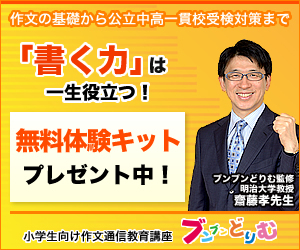
![にゃーご (ひまわりえほんシリーズ) [ 宮西達也 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7902/79026077.jpg?_ex=128x128)


















































































































































コメント