
他にも、子どもが学校行ったのに
「水筒が家にある!」「筆箱がなんでここに?」などと焦った経験も・・
何度言っても、言ったことすら忘れちゃったり、入れたつもりだったり、なかなか直らないとどうしていいのか分かりませんよね。
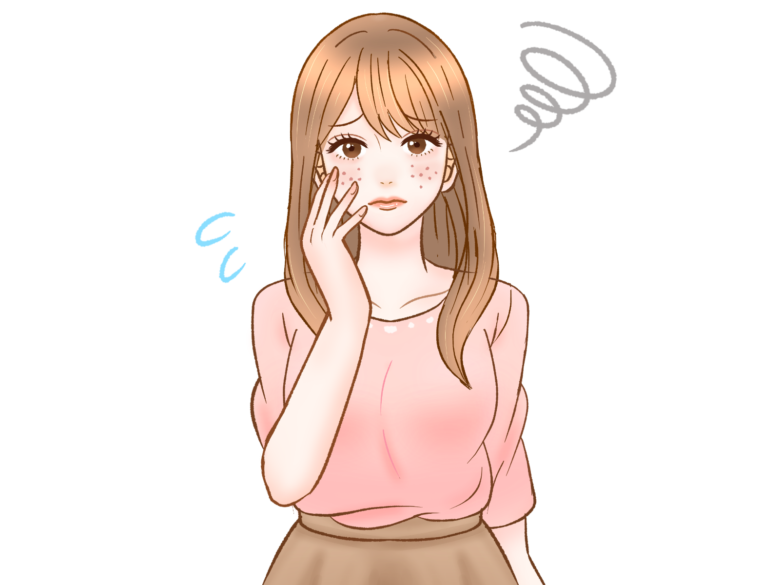
忘れて困っている子どもを想像すると、学校まで届けるべきかも悩むところです。
今回は、子どもの忘れ物が多い時の対処法や、忘れた時に親が届けるべきかなどをまとめました。
子どもの忘れ物が多い時の対処法
学校へ持っていくものを忘れてしまう時の対処法を紹介します。
忘れ物をしないことは今も大切ですが、大人になってからもとても大切なことです。
社会人になってからの忘れ物は、まわりにも迷惑を掛けてしまいます。
今のうちにしっかりと定着することが、大人になってからの仕事や生活にも必ず役に立ちます。
ただ、これをやればすぐ直る!というものではないので、焦らずにゆっくりサポートしていきましょう。
習慣化できるまで一緒に準備する

もしかしたら、きちんと用意をする方法を知らないのかもしれません。
連絡帳や時間割をみながら、一つ一つ確認しながらランドセルに入れる作業を子どもと一緒にやってみてください。
次の日の用意を、「なんとなくする」のではなく、「しっかりとやり方を習慣化する」ところまで教えなければなりません。
「明日の準備した?」と確認するだけではなく、一緒に確認しながら準備をしてみてください。
時間割などには教科の名前しかないので、その教科には何が必要なのかも一緒に考えます。
すっと学校に保管している教材などもあると思いますが、念のために家にないか確認します。
不定期に自宅保管する時や、宿題で持って帰る時もあるからです。
全ての確認を習慣化できるまで一緒にやることが大切です。
夜寝る前に準備して、朝出かける前にもう一度確認することも習慣化するとさらにいいです。
持ち物チェック表を作る
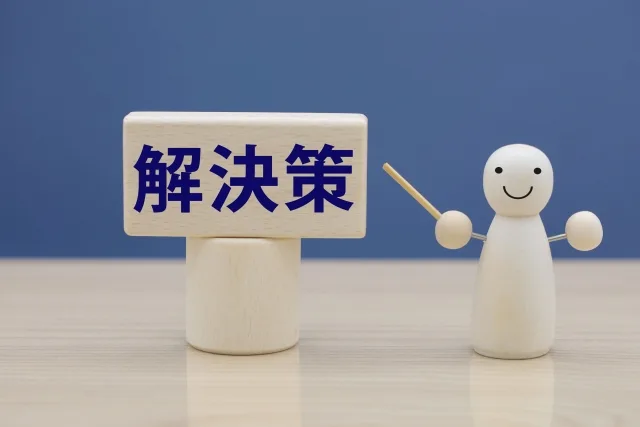
毎日のことですが、学校へ持っていくものは意外とたくさんあります。
子どもが何人もいると、親も結構大変ですよね。
毎日必要なものもあれば、その曜日だけ必要なものもあり、さらにはイレギュラーで必要なものも結構あります。
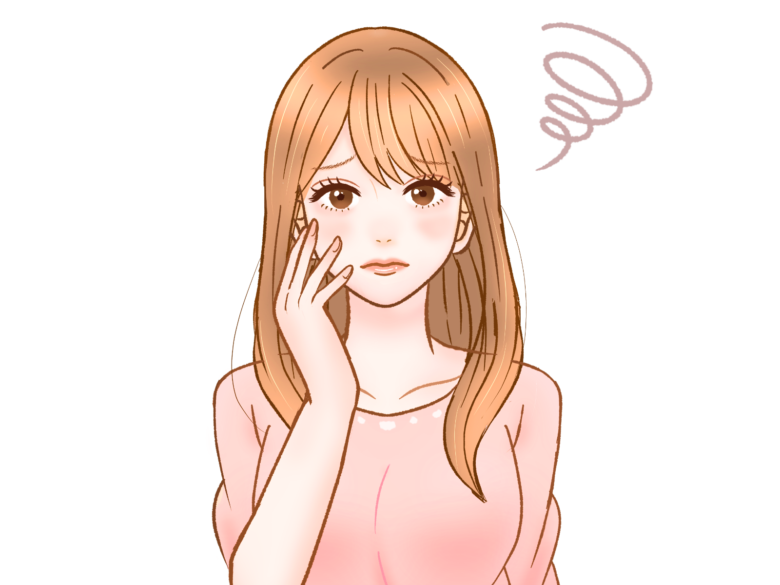
連絡帳や時間割を確認して準備したのに、毎日持って行くはずのハンカチや水筒・帽子などを忘れちゃったなんてこともありますよね。
そうならない為にも、毎日持って行くものもチェックできるチェック表を作成します。
毎日持って行かないものも、チェックリストに入れておくと、「それは明日は必要ないね」と全て確認することもできます。
自分で項目も考えて作ってもいいですし、市販のチェック用品を使ってもいいと思います。
忘れ物をして困る体験をさせる
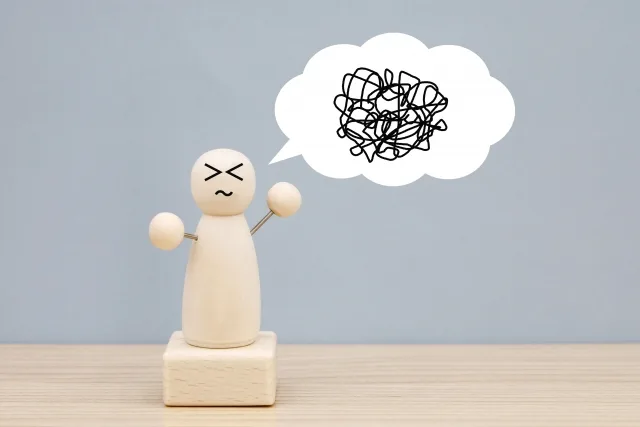
いつも親が声を掛けたり準備をしてあげたりしていると、子どもはそれが習慣になります。
すると、親の手助けや声掛けがないと忘れ物が多くなります。
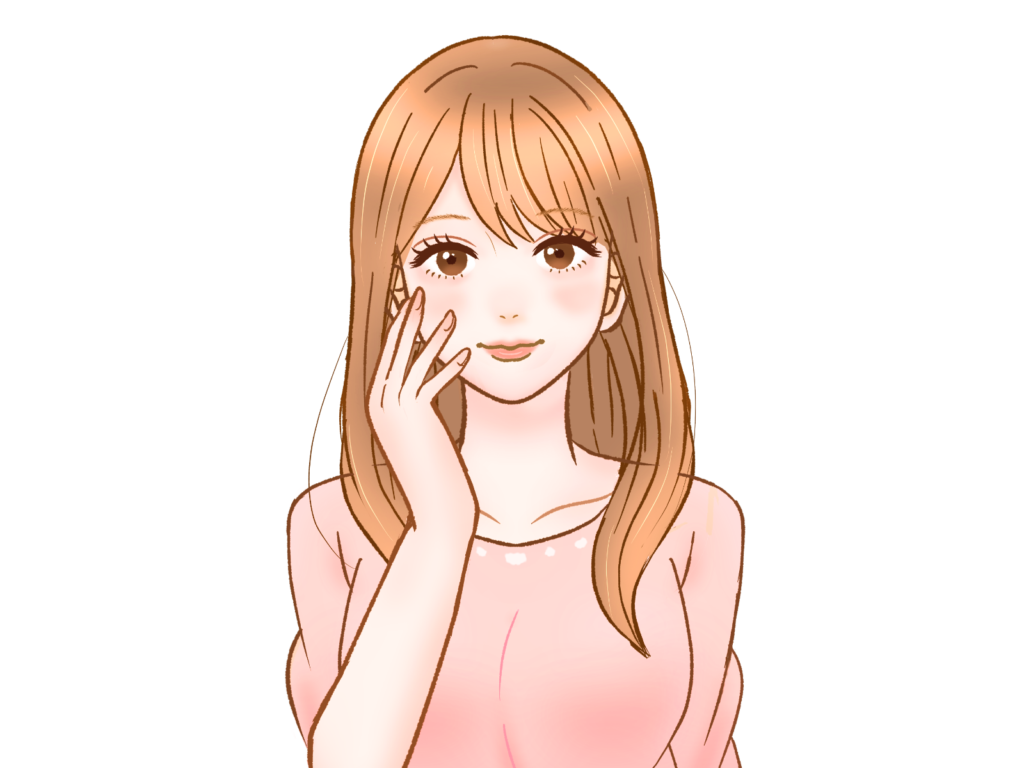
子どもが学校で困らないように・・という想いから、つい「ハンカチは持った?」「今日図工があるんじゃないの?」などと声を掛けてしまいますよね。
しかしそれが続くと、子どもは自分で考えて準備をしなくても忘れ物をしない環境になってしまいます。
そして、自分で「忘れ物ないかな」と確認することもしなくなります。
声を掛けたい気持ちをグッとこらえて、子どもに任せることも必要です。
そうすることで、子どもが忘れ物をしてしまい、自分が嫌な思いを体験できます。
失敗体験は、子どもが成長できる大きなチャンスです。
自分で体験した時は、次は忘れ物をしないようにしよう!と思います。
子どもの成長に役立つ>>感性と思考力がぐんぐん伸びる【ワンダーボックス】 ![]()
チャイルドコーチのワンポイントアドバイス

子どもが忘れ物をした場合の対応で正解はありません。
親御さんが、お子さんのためにどんな方法がいいのか考えていることは、それだけでとても素敵なことです。
子どもが宿題を忘れたり、持って帰って来るのを忘れたりした時は、落ち込まないでください。
失敗は、子どもが成長できる大切な機会です。
これは作ろうと思ってできる機会ではありません。
失敗をして、「その時どうしたらいいのか」「次はどうしたら失敗しないのか」、これらを考えることが、この先の人生にとって大きな学びになります。

子どものうちは、何度失敗してもいいんです。
たくさん失敗した子は、大人になって失敗することも少なくなります。
そして、もしも失敗してしまっても、それを乗り越えていく力を身につけています。
子どもが忘れ物をした時は、「よし!成長できるチャンス!」と心の中で喜んでください。
子どもの忘れ物を親が届ける?

子どもが学校へ出かけた後、机の上に宿題を発見!
どうするべきか悩みますよね。
昨日、宿題を頑張ってやっていた姿を思い出すと、届けてあげたい!
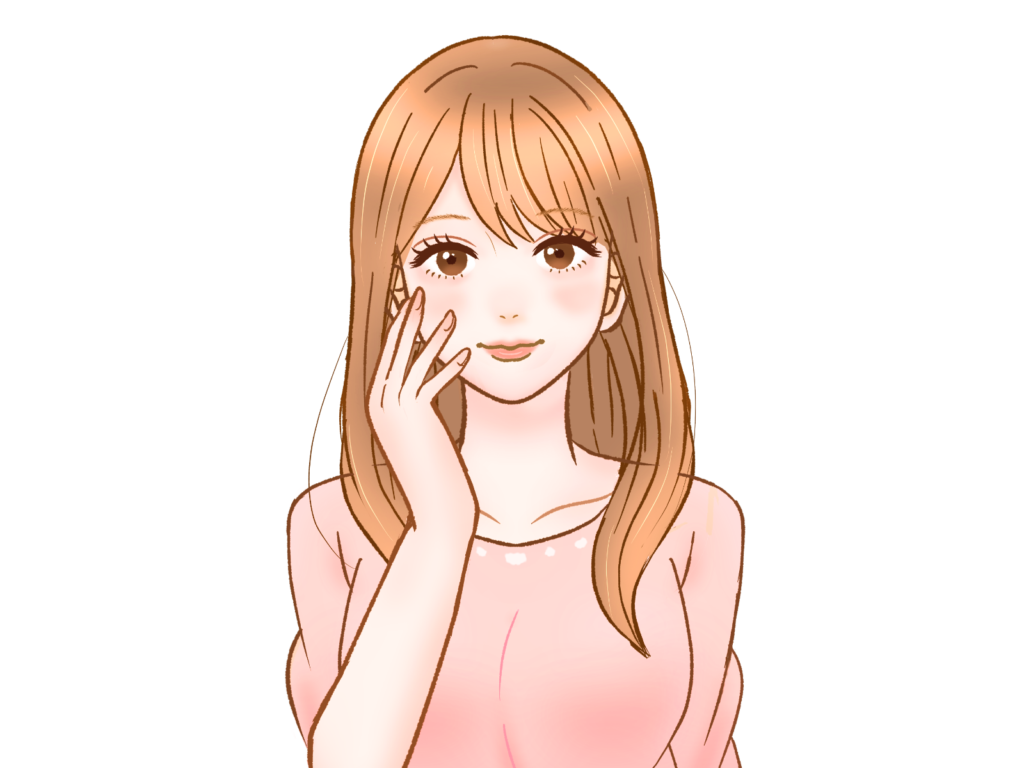
でも、届けない方が子どものためにはなるし、また忘れても届けてもらえると甘えもでるかもしれないし・・と色々考えてしまいます。
結論としては、届けない親が多いです。
しかし、届けないべきと分かっていても、届けてしまう場合や、周りの子に迷惑が掛かってしまうものは届ける方も結構います。
忘れ物は届けない派

親が届けてあげることは簡単です。
本人が先生に注意されて、次から気を付けることの方が子どものためになります。
子どもが困らないようにすべてフォローして、今後のその子の人生はどうなるのかが心配です。
社会に出てからもフォローし続けることは過保護です。
子どものうちに本人が困って、この次は忘れないようにしようと思うことは大切な経験です。
そういった経験がないと、本人が大人になってから苦労します。
自分が子どもの頃に、親が頻繁に忘れ物を届けてくれていました。
大人になって、忘れ物が結構多いです。
大人になってから痛い目に合うのはとてもキツイです。
なので、自分の子には絶対に持って行かずに、子どものうちに学んでほしいです。
「忘れ物があっても、子どもが困り次から忘れないように注意することができる大切な機会なので、届けないでください」と学校から通達があります。
学校の方針や担任の先生によるかもしれませんが、その考えに同調しますので届けていません。
忘れ物の種類による派

次の子に回す給食着や、調理実習で分担した材料などは持って行きました。
本人が困ることであれば、手を出さずに経験から学んでもらいます。
しかし、家の子のせいでお友達が辛い思いをすることは見過ごせません。
夏時期の水筒は命に関わる問題なので、持って行きます。
学校で水も飲めると思いますが、教室や通学路で手軽に飲める水筒がないと、子どもは水分を積極的に取らない可能性があります。
熱中症は、本人の自覚症状がなくてもありますので、対策として水筒は持たせておきたいです。
家のカギを忘れていた場合は届けます。
わが家は共働きで、子どもが帰る時間には居ないことが多いです。
家に入れない時の危険も多い世の中なので、それは届けてあげます。
忘れ物を届ける派

家を出てすぐの時や、ランドセルを忘れている時はさすがに追いかけました(笑)。
本来は家の近くであっても、本人が気付かなければ忘れさせた方がいいのかもしれません。
しかし、まだ玄関を出てすぐや、集合場所にいる時などは届けてしまいます。
学校までは届けません。
小学校の時ではありませんが、中高生の時は何度も持ってきてもらっていました。
厳しい先生の忘れ物は本当に困るものなので、私はとても助かりました。
なので、私も届けてしまうかもしれません。
子どもの成長に役立つ>>感性と思考力がぐんぐん伸びる【ワンダーボックス】 ![]()
宿題を学校に忘れてきたら取りに行く?

宿題のプリントを忘れてきたり、国語の教科書を忘れて音読できなかったりなどもよくありますよね。
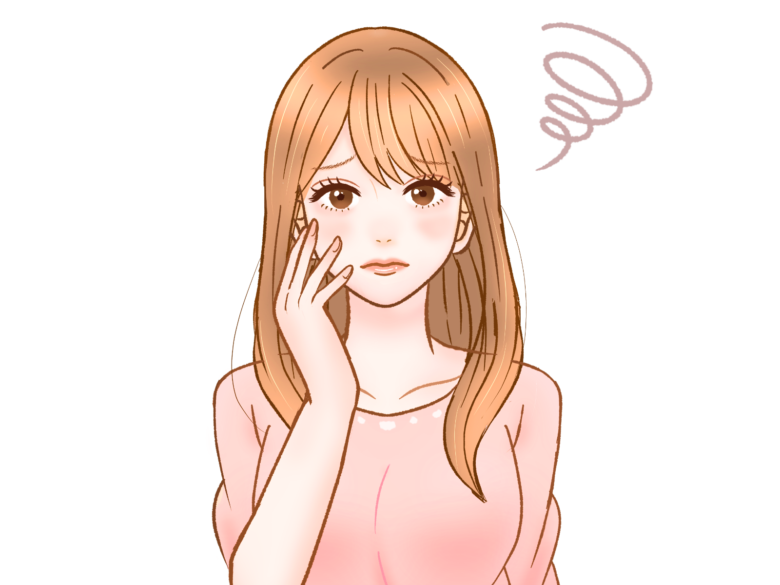
宿題をできないと子どもも親もどうしよう・・と悩みます。
そこで学校へ取りに行って宿題をやっていく方がいいのか、忘れたことを反省する意味もこめて取りに行かないべきなのかをまとめてみました。
取りに行く派、取りに行かない派、学校の対応による違いもありますが、同じくらいの様です。
学校に取りに行く派

学校が宿題を忘れてもペナルティなどがありません。
やらなくても次から気を付けようということに繋がりません。
ですから、自分で取りに行って宿題をやることの方が、本人にとって次から忘れないようにしようという注意に繋がるからです。
自分でインターホンを鳴らして、先生に説明して教室までは1人で行かせます。
学校に取りに行くことで、遊ぶ時間が減り、本人にとっても反省する事由になります。
失敗を放置するより、自分で責任を持って解決する方が大切だと思います。
忘れた物は、自分で取りに行くのが責任です。
子どもが取りに行きたくないと言うなら、取りに行かず次の日に先生に叱られたらいいと思います。
学校に取りに行かない派

放課後は安全面や先生方への負担から、下校後は入ることを禁止されています。
そういった制約がある学校は、必然的に取りに行けません。
しかし、禁止されているが、取りに行ったら開けてくれるという学校もあるようです。
「忘れたら取りに行けばいいや」という思考になりそうなので取りにはいきません。
どうしても必要なものであれば行きますが、学校に取りに行くことが苦ではない子には、一度行くと「また忘れてもなんとかなる」という気持ちになり、気を付けなくなってしまいます。
学校ではなく、近所の友達にコピーしてもらったり、写真を送ってもらったりしています。
問題集やテキストなどは別ですが、プリントや音読などはコピーでもできます。
お互い様で、忘れた時は持ちつ持たれつでやっています。
困る経験も大切なことなので、自分で困ったことを反省してほしいです。
次からは忘れてこないようにする習慣をつけたいです。
学校に忘れてきて宿題が出来ず、次の日に先生に叱られたり、休み時間が宿題で潰れてしまったりすると、本人に忘れないようにしよう!という気持ちが生まれると思います。
まとめ

- 親も一緒に準備をし、やり方を教える
- 子どもが準備を習慣化できるまで付き合う
- チェック表を用意して、忘れ物がないか分かりやすくする
- 子ども本人に困る体験をさせて、自分で忘れないように意識させる
親は届けないことが多い
【例外で届けるもの】
- 周りに迷惑を掛けるもの(順番に使う給食着や調理実習の材料など)
- 命や危険に関わるもの(水筒や家のカギなど)
学校の規則や先生の対応や、子どもの性格などで意見が分かれる
学校の様子がある程度分かれば、判断もできます。
しかし、まだ低学年であったり、子どもが学校のことをあまり話さない場合などは、様子が分からずに悩まれる方も多いと思います。
もしも、ご自身で判断できない場合は、学校の先生に相談してみるのも有効な手段です。
お子さんと、親御さんにとって最良な対応がみつかれば幸いです。
子どもの成長に役立つ>>感性と思考力がぐんぐん伸びる【ワンダーボックス】 ![]()
最後までお読みいただきありがとうございました。



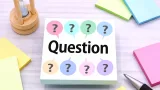


コメント